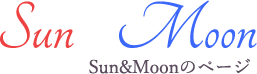大人っぽくなってよ
2005.1
「今日子さん、もっと大人っぽくなってよ。」
二男から初めて来た年賀状にはそう書かれていた。ご丁寧にも黄色のラインマーカーで線まで引いて。彼は私がまた彼に抱きついたりしないかと心配しているのだ。遠く離れて暮らしているために、いつも私に甘えることができないから、意識的に距離をおこうとしているのだろう。
二男のたっての頼みとあらば聞いてやるのが筋なのかもしれないが、それは私にはできない相談だった。それでは自分に嘘を付くことになってしまう。二男を怒らせることになるかもしれないが、私は二男に会ったらこう言おうと心に決めた。
「それは無理よ。今日子さんは子供っぽくしかなれないの。」
一九九一年の暮れ、私は四谷にあるダイヤモンドのショールームにいた。普段宝石などにとんと興味のなかった私だったが、そのときはなぜか急にダイヤモンドが欲しくなったのである。それで、世界で最も美しいと言われるカットのダイヤモンドを見に行った。中でも一際美しい光を放つダイヤにしばし見とれていた。もしも買うならこれしかないな。でも高いだろうな、と値段を訊いてみると、案の定、これは最も美しいカットのダイヤで、残念ながら売り物ではありません、という答えが返ってきた。仕方なく、その場にしばし止まって、その波動を感じていた。
二男を身籠もったのはその夜のことである。夫は私にとって保護者のような人で、はっきり言って、お互いにとって「男」と「女」ではなかった。だから、長男を妊娠してからそちらの方はさっぱりだったのだが、なぜかその夜、夫が急にその気になった。事に及んでいる最中に夫が突然何かに驚いたようにこう言った。
「今誰かが入ってきた。」
私は元来鈍感なもので、そのときも全く何も感じなかった。けれども、その後はそれが一切なかったにもかかわらず妊娠したのだから、二男は間違いなくあの夜にやって来たのだ。
私が「運命の男」と呼べる人に出逢ったのはその六ヶ月後のことだった。彼は私にとってまさに「男」であった。私はその凄まじい引力に驚き、苦しみ、必死で抵抗した。あの頃の私には家庭を壊す勇気は全くなかったし、それが正しいことだとも思わなかった。私の中から沸き出していたのはまさに正真正銘の愛だったにも拘わらず、私はそれを押さえ込むのに必死だった。故に私の生命力は枯渇し、心身に共に病気になってしまったのである。二男を生んだ後はまさに地獄そのものだった。
何ヶ月も眠れない日々が続いた。体はやせ細り、風邪をこじらせて肺炎になった。強い薬を飲んだら、そのダメージで体はさらに弱った。毎日、明日死ぬ、明日死ぬ、と思っていた。
たまにふっと眠くなって眠れそうになるときがあった。ここで眠れたら少し楽になる、と思ったそのとき、二男が泣き出した。「どうして泣くの? 私はあなたのために生きていたいのに!」私がそう言うと、二男はさらに激しく泣いて私の眠りを妨害した。それはまるで、私を殺そうとしているかのようであった。
それが致命的な一撃となって、私はついに白旗を揚げざるを得なくなったのだ。夫にすべてを正直に話したのである。
私が離婚を決意したのは長男の導きによるものだったが、その前に、夫に正直にすべてを話すことを私に強要したのは二男であった。二男のあの残酷なまでの仕打ちがなかったら、私はきっと誰にも話さずに我慢し通してしまっただろう。そして自分に嘘を付いたまま、半分死んだまま人生を終えたに違いない。
二男はきっとあのとき私にこう言いたかったのだ。
「僕のために生きていたいなんて嘘だ!あの男のために生きていたいんだろう?正直になってよ!」
離婚したのは二男が二歳の時だった。その後、すぐに元夫は再婚したので、二男にも新しいお母さんができた。だから物心が付いた頃から私は二男にとってお母さんではなく、今日子さんだった。もちろん、私が生みの母であることは知っていたが。
長男はまさしく離婚の仕掛け人だったので、両親の離婚についての完全な理解者だったが、二男にとっては寝耳に水の話であった。でも、そのことについて説明するには、彼はあまりにも幼すぎた。
新しいお母さんはとてもいい人だが、それでも心から甘えられる生みの母から離れているということは、二男にとって辛いことだったのだろう。前回会いに来たときには、私が抱きしめると彼は嫌だ嫌だと言って激しく抵抗した。大声で泣き叫ぶ彼を私はさらに強く抱きしめた。生みの母の前で泣いたりわめいたりすることが、彼にはどうしても必要なのだという気がして。すると彼は吐き捨てるようにこう言った。
「どうして離婚なんかしたんだよう!」
「パパとママは本当の相手じゃなかったの。今のお母さんがパパの本当の相手なのよ… 」
私が離婚したくなくて自分に嘘を付いていたとき、そんな私を許さないで殺そうとしたのはあなた自身なのよ、などとはとても言えなかった。それではまるで、「あなたのせいで離婚する羽目になったのよ。」と言っているようなものだ。私が運命の男と再婚を果たした曉になら胸を張って言えるだろう。「私をこんなに幸せにしてくれたのは、あなたなのよ。」と。でも、今はまだ言えない。
一年半ぶりに再会する前に、「大人っぽくなってよ」と釘を刺されたけれど、私はまたきっと抱きしめてしまうだろう。それはどうしようもないことだ。彼はまた激しく抵抗するだろうか?
意外なことに、私が「子供っぽくしかなれないよ。」と言っても、彼は一つも怒らずに、ちょっとあきれたような目で私を見ただけだった。
リビングでそばに寝そべって、手を握ったり、足をさすったりしても抵抗もしなかった。逆にその手をつねったり、足で蹴ったり、踏んづけたり、私の頭の上に座ったりして、ちょっとした攻撃性を私にぶつけてきた。とても健康的な感じがした。彼は随分素直になった。
やはりどうしても生みの母にしかできないことがある。どんなあなたでも、完全に受け入れる。悪いあなたでも、良いあなたでも、優しいあなたでも、意地悪なあなたでも、すべて許すよ。人にはどうしても、「自分が完全に許された」と感じられる体験が必要だ。自分に自信を持って人生を生き抜くためには。
彼が遊んでいるとき、そばにくっついて背中をなでたりしても、彼は何も言わなかった。それで思い切って抱きついてみた。何も抵抗しなかった。彼の心臓の鼓動が感じられた。限りなく柔らかく、美しい波動を感じた。とても気持ちがいい。まるで私にも羽が生えて天を飛べそうなくらい。これはあのときのあのダイヤモンドの波動だろうか?この子はあのダイヤモンドの波動を持っているのだろうか?
彼もきっと気持ちよかったに違いない。口では「気持ちわりー」なんて言っていたが。彼も本当は抱きしめて欲しかったのだろう。
「愛してるよ。」
「そう。」
「また来てね。いつでも待ってるよ。」
「うん。」
見送りの電車の中で涙を溜めていた私を彼は黙って見つめていた。前よりも随分理解し合えたような気がする。でも、まだすべてを話せてはいない。
彼にすべてを話すためには、私が幸せにならなくては。私が本当に幸せになってこそ、彼は今までに起きたすべてのことを理解し、納得するだろう。そのときになったらすべてを話そう。
あなたは私を殺そうとしたのよ。でもそれは正しかった。あのとき私は自分に嘘を付いていた。あなたはそれを決して許さなかった。それは私にとってあまりにも過酷な拷問だった。だからあなたを恨んだりもしたわ。けれども、あなたがそうしてくれなければ、私は嘘を付くことをやめることができなかったの。あなたのお陰で私は正直になれた。だからこそ幸せになれたのよ。あのときあなたは私を本当に愛してくれたんだ。私の本当の幸せを願ってくれたんだ。今だからそれがわかる。本当に、ありがとう。
(二松学舎大学散文サークル『ぬるま湯』30号 付録)