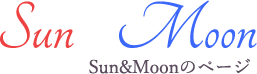片想いのススメ
人に自慢できることは何一つないが、ただ片想いの数だけは誰にも負けないのではないかと思う。とにかく惚れっぽい性質で、高校時代にはクラスメートの男子生徒の半分近くを好きになってしまったほどである。それもいい加減に好きになるのではなく、どの場合も実に真剣であった。
ごく普通の友達として気軽に接していた人なのに、ある日突然、好きだということに気付いてしまった日から、すべてがぎこちなくなってしまう。自然に振る舞おうと思えば思うほど、まともに話しかけることもできず、近寄ることさえできなくなってしまう。ところがそのうち、相手から話しかけてきたりすると、ひょっとしたらこの人は私のことが好きなのではないかと思ってしまう。そう思い始めると相手の行動の一つひとつがみなその証拠のような気がしてしまって、しばらくはその喜びに有頂天になるのだが、ある日、それがすべて思い違いであったことを知り、張り裂けんばかりに泣いてすべてが終わる、というその繰り返しであった。
ところがそんな私でも唯一好きになることができなかったのが、私のことが好きだと言う人であった。というのは、彼らは本当の私を見ているのではなく、勝手に私の像をつくりあげてしまっているのだから、いつかは私の化けの皮が剥がれて愛想をつかすに違いない、と感じて鳥肌が立ってしまうのである。そんなわけで私の恋は一度として成就することがなく、母親が呆れ果ててしまうほど失恋を繰り返してばかりいた。
しかしそんな中で、成就しようがしまいが、誰かのことを好きでいるときは、人生自体が生き生きとして、何をしていても楽しくなるということに気付き始めていた。そして度重なる失恋に、ついい恋の成就自体を望む心すら薄れていくようになった。
なかでも決定的に打撃を与えたのは学生時代の先輩だった。卒業した後も度々遊びに行こうと電話をしてくるので、これはもうきっと私のことが好きなのだと思い込んでしまったのだが、その度にどういうわけか私の友人を連れてこいと言うのであった。当然のことながら、ある日、それは彼が私の友人のことが好きだったからだということが判明した。私が泣きながら自分の気持ちを告白して、もうこんなことはやめてほしいと言うと、彼は驚いて、君の気持ちは全然知らなかった、と言った。その時私には、彼を憎む気持ちは一つも起こらず、彼が幸せになることを心から望みながらもなお、彼を好きでいられることに喜びを感じていたのである。
そんなわけで、次第に見返りを求めないで人を愛することができるようになったのだが、その思いの丈を知ってもらいたい、という欲望だけはどうしても捨てることができなかった。「あなたが好きです」と言って空気を抜かないと、心がその想いで膨らんで破裂してしまいそうになるのである。それで「何も望まないし、何もしてほしくありませんが、あなたを愛しています」などという長文のラブレターを送り付けて、相手を仰天させてしまったこともある。しかし相手が独り身ならいいが、家庭を持っていたりする場合、下手をすれば相手の平和を乱してしまうことになりかねない。愛するということは、相手の幸せを望むことなのにである。
ある時、しばらく一緒に仕事をしていた人を好きになってしまった。その仕事が終わりに近付き、もうそろそろお別れだから、別れる前に何か一言言いたいと思っていたところが、何も言わないうちに会えなくなってしまった。何か言わなければ破裂してしまいそうなのに、奥さんのいる家にラブレターを送り付けるわけにはいかない。
思案の末、彼の仕事ぶりが見事なのに感動したから、これからも大いに活躍してほしい、というような主旨のはがきを出したのである。するとなんと奥さんから返事がきて、とても嬉しいはがきで、それを肴に家族の会話が弾んで楽しい夜を過ごした、と書いてあった。私の愛が楽しい夜に変質して彼の家庭に届いたのだ。私は自分の恋がまぎれもなく成就したことを感じた。
ある時、私の人生の恩師が一冊の本を持ってきた。『The Giving Tree』(惜しみなく与える木)という本である。日本語訳は『大きな木』(篠崎書林)で有名な本だから、知っている人も多いかもしれない。
ある林檎の木と仲良しの少年がいたが、成長するに従って恋人や金儲けの方が大事になり、木には見向きもしない。何かが必要な時だけ木の所にやってきて、林檎も枝も幹も全部持っていってしまう。それでも木は幸せだった。最後に切り株だけになった木の所へ、老人になった少年がひょっこり帰ってくる。木は泣きながら言う。「ごめんなさい。もう何もあげるものがありません」「いや、もう何も要らない。私は休みたいだけだ」と彼は切り株に腰を下ろす。それで木は幸せだった、という内容である。
その頃私には、生まれて初めての恋人がいた。これほど多くの片想いの末、やっと巡り会った恋人だったから、私にとっては何物にも代え難い貴重な人であった。にもかかわらず、師が私に木のようになれと言っているのは明らかだった。惜しみなく与えることならできるかも知れない。でも、彼をしっかりつかんでいなければ、彼はこの少年のように遠くへ行ってしまって、ほとんど帰ってこないかも知れない。そんなことをどうして受け入れられようか。
しかしその頃、師は私に、人生において最も重要なことは、あらゆる執着を断つことである、ということを何度も何度も語ってくれていた。私自身も、人生のすべての困難は執着から生まれる、という考え方を徐々に受け入れ始めていた。お金、地位、名誉、そんなものへの執着はどうにか捨てられる気になっていた。ただ彼さえいてくれれば! ところが師は、その彼さえ諦めよと言うのである。私には彼すらもつかむことは許されないのか。
涙ながらに、手渡された本を何度も読んだ後、ついに私は師にこう聞いた。
「執着を断たなければならないということはよく分かります。でもすべての執着を断って悟りを開けば、万人を愛するようになると言うではありませんか。そんな私に彼は耐えられるでしょうか。私が彼に執着しないことが彼を苦しめるのではないでしょうか。」
師は言った。
「悟りを開けば万人を愛するようになるからといって、会ったこともない人を、夫と同じように愛するようになるわけがないではないか。悟りというのは、その相手が必要とする分だけ、愛を与えることができるようになることなのだよ。それに人はみな、自分がつかんでいるコップを離せばコップが消えてなくなってしまうかのように思っている。コップを離して机の上に置いてごらん。ほら、コップはどこにも行かずにそこにあるじゃないか。」
私は降伏せざるをえなかった。
私は執着するなという言葉を「好きになってはいけない」「愛してはいけない」という意味だと勘違いしていたのだ。人として生まれて、どうして人を愛さずにいられよう。執着とはむしろ、愛の出し惜しみのことだったのである。十分に愛していないことが執着なのである。よくしてくれないなら、自分の思うとおりにしてくれないなら、遠くに行ってしまうなら、他の人を好きになってしまうなら許せない、というのは愛を出し惜しんでいるのである。自分が愛した分だけ愛が返ってこなければ損だと、愛を出し惜しんでいるのである。
相手がどうであろうとそのすべてを受け入れ、そのすべてを愛してしまって、もしもそれが報われなかったなら、自分が死んでしまいそうな気がして恐いだけなのだ。万が一捨てられたときのために、自分の逃げ道を残しておきたいだけなのだ。逃げ場を失って死んでしまってもよいではないか。そんなことで死んでしまう自分なら殺してしまえばいい。それでもなお死なずに残る何かがあるのだから。
許されぬ愛などあり得ない。この人を愛してはいけない、などと言って愛を押さえつけてしまえば暴走するだけである。むしろ、全身全霊をこめて愛すればいいのだ。客観的に成就し得ない愛であっても、全的に愛することさえできれば、愛すること自体がよろこびであり、成就なのだから。その愛は無尽蔵であり、誰一人傷付けることなく、みなを幸福に導くエネルギーとなって働くだけなのだから。
そしてその相手が本当に自分にとって必要な人なら、その人は決して離れていったりはしないのだ。相手を遠ざけるのはむしろ執着の方だったのである。全的な愛は相手に安らぎを与え、かえってそばに引き寄せる。つかんでいなければ離れていってしまう、という考えは完全な錯覚であった。
また、たとえ愛する人ともう二度と会えなくなったとしても、その深い悲しみすら、実は深い喜びにつながっていることを知るだろう。なぜなら、愛すべき時に、愛はただの一瞬も無駄にせずに流れ続けたからである。愛を出し惜しんだ人だけが別れに泣く。あの時もっと愛せばよかったと。
このような愛を地鶏の子育てに見た。ひなが親鶏を必要としている時、親は全身全霊をこめて雛を愛し、守り、育てる。ひながかえるまでの三週間あまりは巣から一歩も出ずに卵を抱き続け、小さなひなの前に敵が現れれば身を挺してかばい、ひなのためにえさを探すのに何の苦労もいとわない。
ところがひなが成長して独り立ちしなければならない時がくると、親はもうひなに見向きもしないのだ。ひなが愛を必要としている時に全的に愛したゆえに、親離れする時には一切の未練がないのである。
* *
ある時、待ち合わせの場所に行くのに道に迷ってしまった。電話をすると車で迎えにきてくれると言う。車に乗り込んだその瞬間、突然、なぜ道に迷ったのかが分かった。私はこの人と一緒に車に乗りたかったのである。気付いたとたんに愛が流れ出したのを感じた。ほんのわずかの時間であったけれども、私は「恋人」とのドライブを思う存分楽しんだ。もう何を言う必要もなかった。
彼が敏感な人だったら、その場の暖かい雰囲気に気付いたかも知れない。でも、気付こうが気付くまいが、私は愛のエネルギーが確実に彼に届いていることを知っていた。私の恋はそれに気付いた瞬間に成就した。
* *
私が度重なる片想いの末に知った、片想いの極意はこれであった。このような片想いを夫婦が互いにすることができたら最高ではないだろうか。
追記 あまりにもたくさんの片想いをしたので、これを読んだ方の中に思い当たるフシのある方がいらっしゃるかもしれませんが、「これはひょっとしたら、私のことではないでしょうか」という質問だけはご勘弁願います。 1992年 4月
今読み返せば、このころの私にはまだ守っているものがありました。ですから、この文章にも、何かを隠そうとして正直に書かなかった部分がいくつかあります。何よりも当時の私は、決定的に重要なある一つの恐ろしい事実を知らないでいました。
それでも、この文章を載せようと思ったのは、これが私が彼に出逢う直前に書かれた文章だからです。私は恐いもの知らずにも、このようなことを考えていたまさにそのとき、彼に出逢ったのです。
2004.1.22(陰暦1月1日)