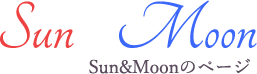韓国遊学記(2)
友人から「丹田呼吸の先生はとても智慧のある素晴らしい方だ」と聞かされていた私は、そこに現れた、背が低く、小太りの若い男…慧元(ヘウォン)を見て面食らってしまった。髭を生やしたもっと貫禄のある年輩の男性を想像していたからだ。彼の当時の年齢は28才で、私と三つしか違わなかった。
けれども、毎日のように彼がやって来ては話すことを聞いているうちに、私が彼を心から尊敬し信頼するようになるには、それほどの時間はかからなかった。彼は学歴こそないが(実は小卒であることを私は最近になって知った!)、話の内容はどんなに偉い大学の先生よりも深かった。何よりも驚嘆したのは、彼が問題解決能力を持っていたことだ。どんな悩み事でも、彼と話しているうちに解決の糸口を見つけることができたのである。
私が当時学問の世界で研究活動をしながら痛切に感じていたのは、「知識の限界」であった。問題解決のために知識を動員しようとすれば、厳密に言うなら、際限がない。常により正確な、より豊富な知識が求められ、結局最後に辿り着くのは、「本当の問題解決のためにはさらなる研究が必要である。」という結論でしかないのだ。いつも不完全な解答しか得られないのが学問の世界であり、その不完全さを完全に少しでも近づけるために努力することにこそ価値がある、というような考えに支配されている。完璧主義的なところがあった私は、本当の答えを得るために自分が知らなければならない事柄の膨大さ(無限さ?)に直面して途方に暮れていた。
慧元が問題解決のために知識を駆使しているのではないことはすぐにわかった。彼は明らかに、その場の「直感」で話をしていた。にもかかわらず、驚くべきことに、それはどんな博識な研究者の提示する解決策よりも見事であった。本当の問題解決のためには「知識」は必要がないということを彼は証明して見せてくれた。彼はまさに自分の中の「智慧の泉」を掘り当てた人だったのである。そして、私もまた、自分の泉を掘り当てたいと切実に願うようになった。
丹田呼吸の話をしそびれてしまった。彼はもちろん、毎日呼吸法についても教えてくれたが、それを実演なしに言葉で説明するのは難しいから、ここでは割愛しよう。
彼が当時を振り返って言うには、「あなたはとてもいいものを持っているように感じられたが、ひどく混乱していた。その混乱を取り除いてあげたかった。」彼にとっても、本当に大切だったのは呼吸法でなくて話の方だったと思う。
学問の世界は、私に本当の問題解決方法については教えてくれなかったが、とても厳しい指導教授のお陰で、言葉だけはできるようになっていたから、留学当初から私は彼の話を難なく理解することができた。それはとても有り難いことだった。
慧元が最初のころ私にしてくれたのは、こんな話だった。
たくさんの鹿が、道路の上を走っていて、その後からヘッドライトをつけた車が追いかけてくる。光が当たっているのは道路上だけで、両脇は真っ暗である。鹿には明るい道路しか見えないから、車から逃げるために我先に必死で走ろうとする。その両脇に逃げられる広い空間があるなどということは考えもしない。
ところが、何かの拍子にそのうちの一頭が、道路の脇に飛び出してしまった。最初はびっくりしていたが、次第に目が暗闇になれてくると、何と、自由にのんびりできる広大な草原があるではないか! そのことに気づいた鹿は、走っている仲間たちを大声で呼ぶ。
「おーい、こっちに来てごらんよ!広くて快適だよ!」
けれども、暗闇を恐れて、誰もその言葉を信じようとはしない。ごくわずかの鹿が、その声に気づいて、暗闇に注意を向ける。そのほかの鹿はただ、走り続けるだけ…
そのとき、慧元は草原の鹿で、私はその声に気づいた鹿だった。私はその言葉を信じて、暗闇に飛び込む決意をした。
あるとき、慧元が一冊の本を貸してくれた。「呪術師と私--ドンファンの教え」カルロス・カスタネダ著、リュ・シファ訳。
(これ以外にも、カルロス・カスタネダの本はいくつか出ているが、「呪術の体験--分裂したリアリティ」「呪師になる--イクストランへの旅」「未知の次元」が面白い。)
翻訳物ではあるが、これが私が最後まで読み通した、最初の韓国語の本である。私はもともと、あまり読書が好きな方ではなかった。特に外国語で書かれている本は、やはり読破するのに骨が折れた。それまでは「読まなくては」という義務感で読んでいたので、途中まで読んで放り出してしまうものばかりだったのである。ところが、この本だけは、最後まで息も継がずに読み切った。私にとってはそれほどまでに引きつけられる本だった。今思えば、私の「体質」にぴったりだったのだろう。
それ以外にも、彼はいろいろな本を紹介してくれた。和尚ラジニーシ、クリシュナムルティ、チベット僧Lobsang Rampaの本、「hope for the flowers」「THE GIVING TREE」のような絵本… このような精神世界の本は、韓国ではかなりポピュラーだった。大学生だったら、みなラジニーシの名前くらいは知っていた。ソウル大にも、インドで修行したことがある、あるいは、修行したいと思っている学生が何人もいた(私の周辺だけかもしれないが…)。
彼は、丹田呼吸を教える以外にひとつだけ私に修行を課した。それは「注視」であった。
「注視」とは、単純に言えば、「自分が考えていることを見る」ことである。慧元は「自分の目で後頭部を見る感じ」と言っていた。何のためにそんなことをするかと言えば、思考を静めるためである。人は常に何かを考えているが、それが混乱を引き起こす元となる。あるがままを見る目を曇らせてしまうのだ。けれども、悲しいことに人は「考えまい」とすればするほど、余計に考えてしまうものなのだ。
「注視」は思考を押さえつける働きではない。自分が考えていることを、ただ、はっきり自覚することである。思考が起こる瞬間をとらえられれば、それは消えると彼は言った。
最初はどうしたらいいのか、さっぱりわからなかった。「注視」をしようとすると、他のことがおろそかになって、蹴躓いたり、何かにぶつかったりした。
慧元は、「やったことがないことを初めてするときは、誰でも難しいものだ。必要なのは練習だけ。慣れれば誰でもできるようになる。」と私を励ました。
それから、彼はいつもこう言っていた。
「やりたくなければ、無理にやらなくていい。」
それで、私はバスに乗っているときだけ、「注視」を練習することにした。最初は自分がどこを走っているのかわからなくて、何度も乗り越してしまいそうになった。けれども、次第に慣れてくると、自分の思考を注視しながら、同時に外の状況も把握できるようになった。そしてだんだん思考は静かになっていった。
慧元は間違いなく私の師であるが、彼は自分が師と呼ばれることを嫌った。彼はいつも「僕はあなたの友達だよ。」と言っていた。彼は我々の間に師弟関係や上下関係を持ち込むことの愚かさをはっきりと自覚していた。だから決して自分を私の上に置こうとしなかった。上下関係が持ち込まれると、必ずそこに「依存」が生ずる。つまり、すべてのことを「師」に頼ってしまうようになるのである。それは必ず自立を妨げる。それでは決して自分の泉を掘り当てることはできないのだ。
世の中には、上下関係を持ち込むことを好む人がほとんどである。自分が他人に必要とされている、他人に頼られている、あるいは、他人に教えることができる、という快感は非常に捨てがたいものである。それで自分の存在価値を確認できるような気がするから。だから世の中の多くの「師」は大勢の弟子を抱え込み、それで自分がさも価値のある人間であるかのように思い込む。けれども、それでは本当に大切なことは何一つ伝わらないのだ。
人間の本当の存在価値はもっと別のところにある。そのことに気づくのは、実は容易なことではない。
慧元が私の師でありながら、私を自立させてくれたことは、とてつもなくありがたいことであった。それは本当に難しいことなのだ。お陰で、私も彼のやり方を踏襲することができるのだから。(続く)