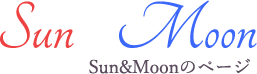「言語音、声」
簡単に言えば、言語には「音」と「意味」という二つの要素がある。
言語音について扱う分野は音声学と呼ばれる。そこで普通扱われているのは、舌の形をどのようにすれば、どんな音が出るかとか、その音を機械で読みとればどんな波形になるかという、あくまでも物理的な音についての話である。
けれども、ここで問題にしたいのは、そのような「音」ではなく、「声」である。それが、どの程度の深さで発せられ、心の奥にどこまで響く声であるか、ということだ。それは川田順造氏の言う、「(声の)アナーキーな輝き」*であり、竹内敏晴氏の言う、「自分の声」**である。
先に述べた、現実を創造できるか言葉であるか否かも、その声の深さに関わっていると言ってよい。声が心の最も奥深くから発せられるとき、その言葉は最大の力を持つ。
私にとって、最も深く印象に残っている声は、やはり彼の声だ。自分の本当の相手を見分ける重要な鍵は、声なのではないか。彼の声は、私のすべてを溶かしてしまうほど私の心の奥深くに響いた。彼ほど深く魅力的な声を、私は他に聞いたことがない。誰にとっても、自分の本当の相手の声は、自分の心の一番奥まで響くのではないだろうか。
けれども、大変残念なことに、彼の声ならばいつでもそのように魅力的なわけではない。彼が何かを繕っているとき、虚勢を張っているとき、嘘をついているとき、彼の声は悲しいほど浅くうわずっていて、全く魅力が感じられないのである。特に、2000年3月14日に彼が私に電話をしてきたときの声は、まるで機械の音声を録音したテープを回しているようだった。心も感情も一切こもらない、薄っぺらな声。私が誰なのか分からないふりをしてかけてきたのだから、当然と言うべきか。
声が魅力を失う理由は、どこかが緊張しているからである。全身の力を抜いてリラックスすれば、体の最も深いところから声が出る。だから、ただ何もせずに、ありのままの自分の声を出していればいいのだ。それが一番魅力的なはずなのだ。
けれども、「ありのままの自分の声」を出すことほど難しいことはない。それは私たちが常に「何かしなければならない」という強迫観念に縛られているからである。私たちは、いつも何か「よい」ことをしなければならない、と思っている。「自らの向上の」ため、あるいは、「他人に好かれる」ために。だから、必ずどこかに力が入ってしまう。そのせいで私たちは自分の最大の魅力を失ってしまっているのである。「ありのままの自分の響き」を。
私が彼のありのままの声を最後に聞いたのは、いつのことだったろうか。
彼が私をひれ伏させたかったら、ありのままの自分の声を一言発するだけでいい。それはあまりにも簡単なことだ。あまりにも簡単すぎるが故に、かえってそれができないでいるのかもしれない。
*言語音の直接伝達性あるいは象徴性に、私がおそまきながら"耳を開かれた"のは、日本語に劣らず擬音語、擬態語の豊かな黒人アフリカの言語社会に暮らしてみて、文字を知らない彼らの声の、アナーキーな輝きに触れたからだ。(中略)元来100%声である言語を文字化し、文字を用いて言語教育を行なえば、言葉は規格化される。ことばはよく飼い馴らされ、言語音やことばづかいの個人差や地方差も少なくなって、概念化された意味の通用範囲は拡大されるかも知れないが、ひとりひとりの声が持っていた、くせのある荒々しい伝達力は弱められてしまう。 『聲』川田順造(ちくま学芸文庫)
**ああ、これが自分の声だ、と納得した時、自分が現れる。これが自分だ、と発見するということは、自分をそう見ている自分もそこにしかと立っているということで、ふだんの自分が仮構のものだった。固まった役割を演じていたのだと、霧が晴れたように見える。世界が変わってしまう。目が開く。比喩ではない。実際に相手の顔が、周りの世界の隅々が、くっきりと、初めてのように見えて来るのだ。
深々と息をすると、自分の存在感が変わる。世界のまん中に自分が立っていると気づくと言ってもいいか。自分がこの世に落ち着くのだ。自分の声に出会うということは、自分が自分であることの原点である。 『日本語のレッスン』竹内敏晴(講談社現代新書)