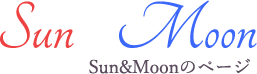「NO BORDER」
最近のCMには、センスのいいものが増えたように思う。時代の流れか。「NO BORDER」というカップ麺のCMもその一つだ。
「冒頭に広大な荒野に引かれている一本の白い線(国境)が現れる。国境を挟んで対峙する人々。実はその国境は無数のカップヌードルでできていた。ひとりの少女を皮切りに次々とカップヌードルを手に取りはじめる人々。やがてその国境は消え、そして、人々の気持ちはうち解けあった。」(「消える国境」篇 制作ノート)
最初にカップ麺を手に取るのが少女だというのも、意味深長である。大人にはなかなかこんな口火を切ることはできないものだ。
言語学においても、文法範疇(カテゴリー)や意味の分類などにおいて、しばしば境界線が問題となる。境界線を明確にしないと、 用語の定義ができないからである。けれども、その試みはいつも失敗に終わる。いかなる定義にも、必ず例外が生じてしまうのである。
これは、言語においてはすべてが「越境」する可能性を秘めていることによる。普段はあり得ない、と考えられる単語のつながりであっても、それを敢えて発言すれば、新たな意味を創造してしまうからである。
例えば、「歩く」という動詞の主語になりうる単語を「動物群」という範疇で分類したとしよう。当然、そこには「机」という単語は入らない。けれども、それでも敢えて「机が歩いた。」と言った場合、その文はそれなりの意味を創造してしまうのだ。たとえ、そのような現実がほぼ100%あり得ないとしても、おとぎ話のような擬人化した机が歩き回る姿を想像するのは、十分可能なのである。
「ことばにそなわる奇妙な条件とは」とポーランは『言葉の贈り物』のなかで書いています、「みずからを破壊する理由をそれ自体のなかにかかえていない語は存在しないということである。語はまるで、その意味を反転させる機械のようなものだ。」
文彩(あや)を許容しない言語というものはありません。
ところで、文彩は意味の侵犯から生じるものです。なぜなら、文彩においてはほとんどつねに、生物と無生物、人間と動物、物質と非物質などの境界の越境がおこなわれるからです。 『言葉の国のアリス』マリナ・ヤゲーロ著 青柳悦子訳(夏目書房)
境界線というのは、そもそも引けないものである。それでも人は何かにつけ、境界線を引きたがる。それはなぜだろうか。多分それは、境界線がなければ、すべてのことが混乱してしまうと思っているからではないだろうか。境界線によって何かの秩序が保たれていると思いこんでいるのだ。けれども、秩序を保つための境界線というものが存在する限り、必ず越境するものが現れる。そこに必然的に生じるのは、絶え間ない葛藤である。苦しみは止むことがない。
おそらく、人が一番保ちたがっているのは、自分と他人との境界線ではないだろうか。その境界線をなくしてしまうと、まるで自分が存在しなくなってしまうかのような恐怖に襲われる。自分と他人との境界線があることで、自分という存在が維持されると思っているからである。
しかしながら、自分と他人の境界線も、いつかは消し去らなければならない。そうしなければ、この世のあらゆる葛藤は決して終わらないからである。けれども、もしもその境界線がなくなれば、「自分」そのものも消滅してしまうのだとしたら、誰も境界線を消そうとはしないだろう。
では一体、どうしたらいいのか。
言語についての考察は、そのことについても示唆を与えてくれる。
ウィリアム・ラボフ(1973)*は、いろいろな形の食器の図を被験者に見せて、それを"cup"と呼ぶ被験者がどれくらいいるかを調べた。その結果、ある形の容器については、100パーセントの被験者が"cup"と呼んだが、それが少しずつ変形して平たくなっていくにつれてその数は減っていき、ある時点で"cup"と呼ぶ者と"bowl"と呼ぶ者が同率になった。つまり、どこまでが"cup"で、どこまでが"bowl"であるという意味の境界線は個人差があって確定できないが、cupという単語の意味の中心(すべての人が"cup"であると認識するもの、典型的なcup)は明らかに存在する、ということである。それがプロトタイプと呼ばれるものである。
私たちは概念についての古典的見解を捨てることにしよう。カテゴリーの基礎にあるものは、プロトタイプに典型的に体現されている「らしさ」であると考えよう。つまり「差異」の設定によってカテゴリーが分類されるのではなく、典型的事例をもとに、同じ「らしさ」を示すものがカテゴリーを形成していくと考えるのである。 『ことばと身体』尼崎彬(勁草書房)
それはまさしく、「自分」にもあてはまる。自分のプロトタイプ(最も自分らしい自分、本当の自分、自分の中心)はまぎれもなく存在するのである。それは自分と他人との境界線が消滅しても、決してなくならない、実在する自分である。
そのような本当の自分、自分の中心を見つけだした人は、他人との間の境界線を消すことを恐れる必要がない。あたかも石を投げ入れたときに水面にできる同心円の波が無限に広がっていき、他の同心円の波と交錯しながらさまざまな波紋を生み出していくように、他人と交わりながら人生を創造していくことができるのである。
というわけで、最後に辿り着く結論はいつも同じである。最も大切なことは、最も自分らしい自分、本当の自分が何であるかに気づくこと。そして、それを教えてくれるのが、自分の本当の相手である。本当の相手との出逢いが、他人との間の境界線を消し去る勇気を与えてくれる。この世から、すべての境界線を消し去る鍵はそこにある。
*『認知言語学入門』F・ウンゲラー/H・J・シュミット著 池上嘉彦ほか訳(大修館書店) による