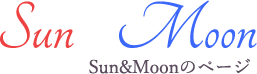『沈黙するソシュール』
言語学を教えることが決まって、本屋で材料になりそうなものを探していたとき、『沈黙するソシュール』前田英樹編・訳・著(書肆山田)という本が目に留まった。
ソシュール(Ferdinand de Saussure 1857ー1913)は「近代言語学の祖」と呼ばれる、スイスの言語学者である。彼は個々の事物が単独で意味を持つのではなく、全体の体系における各要素間の関係性の中でしか意味を持ち得ないことを説いた。いわゆる「構造主義」の元祖である。
この「部分」と「全体」との関係についての考え方は、私にとっても目から鱗が落ちるものであった。『実体と「名付け」の間隙』でも述べたが、「赤い」というたった一つの単語の意味であっても、本当に理解しようとすれば、日本語全体を知らなければならない。つまり、「赤い」という一つの単語の中に日本語全体が含まれているのである。部分は全体を含む。(ということは、私も宇宙の一部なのだから、私の中に宇宙全体が含まれているということになる。宇宙を知りたければ、私自身を知ればいいのだ!)
ソシュールは、21才の時、「印欧諸語の母音の原初体系に関する覚え書き」(1878)という画期的な論文を書いて注目を浴びて以来、次第に論文を書かなくなって、1894年以降完全に沈黙してしまう。『一般言語学講義』という本がよく知られているが、これは彼が晩年に行った講義について弟子たちがノートをまとめたもので、彼自身の著作ではない。そのせいか、この本はかなり難解でいくら読んでもよくわからないところがあった。
『沈黙するソシュール』は、彼が沈黙している間に行った講演の草稿を集めたものである。いわば彼自身の肉声である。この中には、はっとするような、腑に落ちる名言が数多く含まれている。ソシュールはまさに言語を通して真理を究めた人であった。だからこそ沈黙するしかなかった。そのもどかしさが随所に感じられる。(以下の引用はすべて『沈黙するソシュール』。傍点省略。下線を引いたのは私。)
「…けれども、そんなことや、ことばの事象に関して、まともな意味のある十行の文でも書こうとしたらまずつきまとってくる困難やらに、私はつくづく嫌気がさしているのです。私がながいことやってきたのは、何よりこうした事象の論理的分類であり、それを扱う際の視点の分類でした。ところがそうすることによっていよいよ私に見えてくるのは、言語学者に彼が何をしているかを示そうとするときに待ちかまえている仕事の巨大さです。操作ことごとくを、まえもってそのカテゴリーに還元するのですから。したがって、そこで同じくはっきりしてくるのは、言語学で人が最後になしうることいっさいの、とてつもない馬鹿らしさというわけです。」(1894.1.4メイエあての手紙)
最も大まかな要約。
以下は、私が立てようとすることの最も大まかな方向。言語学で禁じられているのは、と言っても、それは綿々と行われいているけれど、ひとつのものをいろいろな視点で語ること、あるいはひとつのものを一般化して語ることだ。なぜなら、ものを作るのは視点のほうだから。こう言うと(たとえば、発声的視点、語源的視点、派生的視点、……的視点でのequos(ラテン語で「馬!」私注)というふうに)たちまち混乱した観点が飛びかうことになる。はじめからequosは、無数の視点から見ていい、つまり何からも独立した、そのへんの事物なみにでっちあげられているわけだ。ところが、やってみるがいい。特定の視点の外でequosを限定するなどということを。
断言するが、視点が区別されれば、そのつど持ちあがるのは、まだ同じ「もの」が目の前にあるのかという問題だ。もしあるとしたら、それはもう桁はずれの偶然、思いもつかないできごとということになる。(p167-168)
言語学と言語についての学を一般化してしまうことは不可能である。どの鉱物でも、鉱物学が教える視点で考えうるし、地球のこの部分、この地層、この時代にそれを生んだ史的異変の視点でも考えうる。特定の局所的な産物だけを考えていて何になるのか。分割に大した利益はないので、ふたつの視点を分けよと言うのは、詭弁にすぎないのではないか。そんな幻覚がとめどなく湧いてくる。そこにまさしく同じ物質があると、私たちは感じているではないか。一方が捉えるのは生成要素の物質的性質であり、他方は価値である。それは、そのとおり。だが、一般化をやってみるがいい。各産物の形成と本質を同時に見ていくなら、どんな一般化も不可能になることが、たちまちわかるであろう。(p233)
私が真理と見える事がらに到達したのは、じつにいろいろな道すじを歩いてであって、他人にはそのうちどれが気にいるのかはわからない。自分の命題を順次そつなく示すには、明確で限定された出発点が要るのだろう。しかし、私がここで立証しようとしていることは、言語学では、それじたいで限定された事象をたったひとつでも認めるのはまちがいだということにつきる。つまり、ここにあるのは、正真正銘あらゆる出発点の必然的な不在というわけだ。(p163)
それに、これは目立った現象ですが、ゲルマン語やロマンス語といった特殊領域の研究に一心に打ち込んできた人々が運んでくる理論的観察は、諸言語の大系列をひとりでかかえこんでいる言語学者の観察などよりははるかに評価され重んじられています。現象のぎりぎりの存在理由が、現象のぎりぎりの細部であるとはなんぴとも知るところで、かくて極度の特殊化だけが、極度の一般化に有効にはたらきうるのです。(p25-26)
「何か」について、語ろうとすれば、まず「視点」を限定しなければならない。けれども、視点を限定することによって、「そのもの」の中のその視点からはずれたすべての要素は無視される。ということは、語っていることは「そのもの」についてではなくて、「限定された視点」についてでしかないことになる。つまり、視点を限定した時点で、すでに語られることは決まっていて、「そのもの」については、何一つ語ったことにならないのだ。
これが言語によって語ることの限界である。結局真実は何一つ「語れ」ない。「感じる」しかないのだ。そのことを知ってしまったら、沈黙するしかないだろう。
「極度の特殊化だけが、極度の一般化に有効にはたらきうる」という一文もまた、彼が次の円の外側ではなく、中心に向かっていることを示している。

一般論を語る必要はない。極度の特殊化、個別化に向かえばいいのだ。本当に全体を知ろうとするなら、個を極めるしかない。自分自身の中に深く入って行き、自分自身を知るしかない。(これはもう何度も語り尽くされた言葉ではあるが。)「最も個人的な話が、最も深い共感を呼ぶ。」かくして私は、最も個人的な話を語り続ける……
ソシュールは晩年、アナグラム研究などに熱中していたと言われる。本屋で見つけた別の本によれば(書名は忘れてしまったが…) 「降霊実験」などもしていたらしい。古代語について本当に知りたければ、実際にその言葉を話していた霊を呼び出すのが最も確実な方法かもしれない。でも、そんなことをしたら、まともな学者とは思われないだろう。
あらゆる情報は、波動の形で存在している、という考え方がある。いわゆる「アカシックレコード」と呼ばれるものである。何かを切実に知りたいと思うとき、思いがけず、ふと、答えを思いつくことがある。アカシックレコードに触れたのである。
何かを知るために、どんなにたくさんの情報を収集し、分析を重ねたとしても、厳密に言えば完璧な結論を得ることはできない。それは結局は徒労に終わる。
それにひきかえ、アカシックレコードから得られる情報は、全く労力を必要としないのに、きわめて正確である。ソシュールが降霊実験をしたくなったのもよくわかる。
では、どうしたら、アカシックレコードに触れることができるのだろうか。その鍵は「感じる」ことにある。